小売業の真空地帯理論とは?意味と具体的な事例をわかりやすく
真空地帯理論は、小売業展開に関する仮設の一つで、1966年にデンマークのニールセン(O.Nielsen)によって提唱されました。市場の変化や小売業の発展によって、既存の小売業がカバーできない市場にすき間(真空地帯)ができ、そこに新たな小売業が参入してくるという理論です。
小売業界は、常に変化する市場で競争するために、自分たちの作戦を常に更新しています。その中で、多くの小売業者が真空地帯理論を採用し、自分たちの商品を他の競合業者よりも優れていると訴求しようとしています。
真空地帯理論とは
真空地帯理論とは、競合業者の商品がある程度質を維持している段階から、競合のない「真空地帯」に入ったような状況を指します。この場合小売業者は、自分たちの商品が競合業者よりも優れていることを強調し、競合のない地帯で需要を増やそうとします。
低価格・低サービス市場に真空地帯ができると、新たな小売業者が参入してきます。やがて小売業は、消費者の好みがレベルアップすることに対応し、グレードアップを図るのです。
グレードアップされた市場には、再び真空地帯が生まれます。その市場では、再び低価格・低サービスの店舗が参入するでしょう。
グレードダウン
真空地帯理論ではグレードアップだけでなく、グレードダウンの考え方もあります。
高価格・高サービスの市場に真空地帯ができると、そこには新たな小売業の参入があります。
消費者の好みが中価格・中サービスであると知ると、小売業は価格やサービスをグレードダウンさせて対応するでしょう。元の高価格・高サービス市場には再び真空地帯が生まれ、新たな小売業が参入してきます。
真空地帯理論は小売業の新規参入の機会が、低価格・低サービスと高価格・高サービスの市場どちらにもあり、グレードアップとグレードダウン両方の流れがあることを、仮定しています。
具体例
具体的に、真空地帯理論について説明します。ある市場に、3つの小売業が存在すると仮定します。
A店は低価格・低サービス、B店は中価格・中サービス、C店は高価格・高サービスです。
B店の人気があるため、A店とC店は、B店のような中価格・中サービスにしようとします。
市場は中価格・中サービスの小売業だけになり、低価格・低サービス、高価格・高サービスの小売業は消滅し、真空地帯が生まれるでしょう。そこに、革新的な小売業が参入してきます。
ソフトドリンク市場に注目してみましょう。この場合、一般的なコーラのようなプロダクトはある程度鮮度が落ちるまでは各ブランドで同じ品質を提供しています。
しかしながら、その品質の劣化が始まると、そのブランドの人気が下がり、他社の新しい商品が登場するまでの間、市場は真空地帯状態になることがあります。小売業者は、その時点で自社のブランドにフォーカスし、鮮度などの特徴をアピールすることで、市場での影響力を増やすことができます。
実践
真空地帯理論を実践するためには、次の3つのステップが必要です。
- 他社の商品と自社の商品を比較して、自社商品をより魅力的にする点を決定します。
- 他社が自社商品と同様の点を謳うことがないように、自社の商品にフォーカスします。
- その魅力的な点を強調する創造的なマーケティングキャンペーンを開始します。
これは真空地帯での需要を増やすための戦略的アプローチであり、小売業者にとって非常に重要なアプローチといえます。
真空地帯のまとめ
真空地帯理論は、競合業者の商品の品質や売上が均等化される際に、自社商品の強みをアピールし、市場での存在感を増やすために非常に効果的な手法です。ニールセン (O. Nielsen) のアプローチによって、商品の比較分析を行い、小売業者は、より魅力的で差別化された商品を提供し、市場での需要を高めることができます。
真空地帯理論とニールセンのアプローチを活用することにより、小売業者は、商品の競争力を高め、自社商品が他社商品よりも優れているというイメージを顧客に与えることができます。あなたのビジネスの競争力を高めるために、真空地帯理論とニールセンのアプローチを検討してみてください。
(このページは2014年に掲載した記事を2021年と2023年に加筆修正更新したものですj)


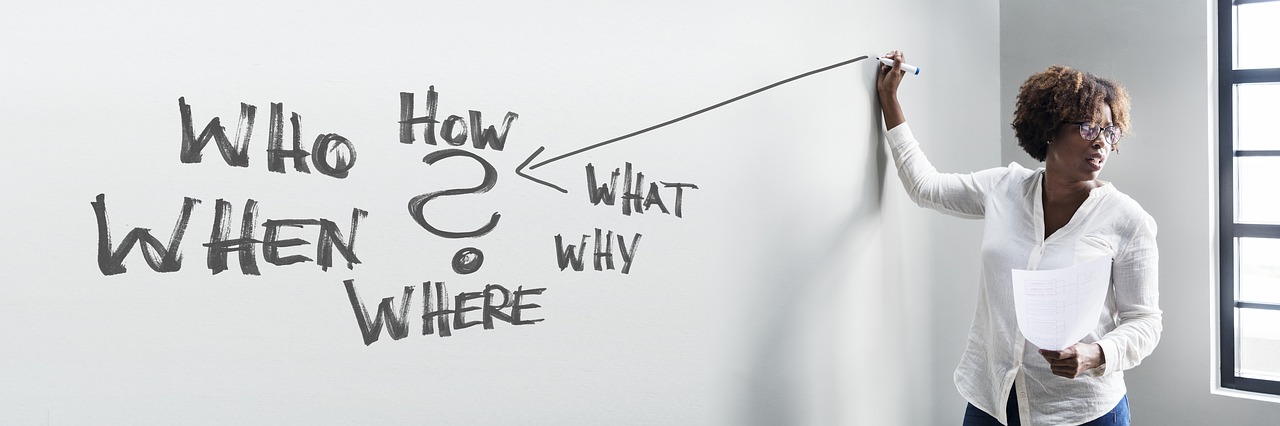
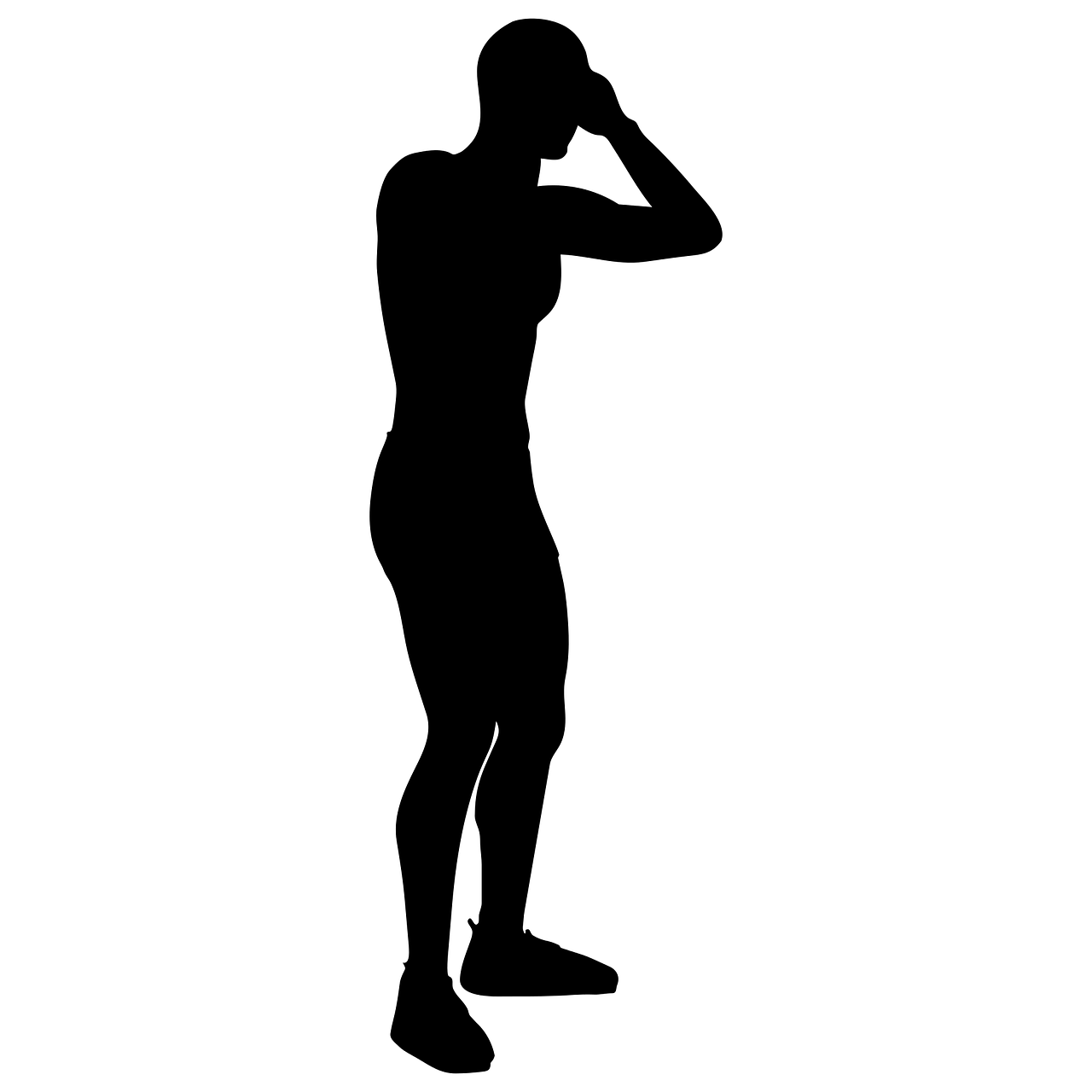





Comment